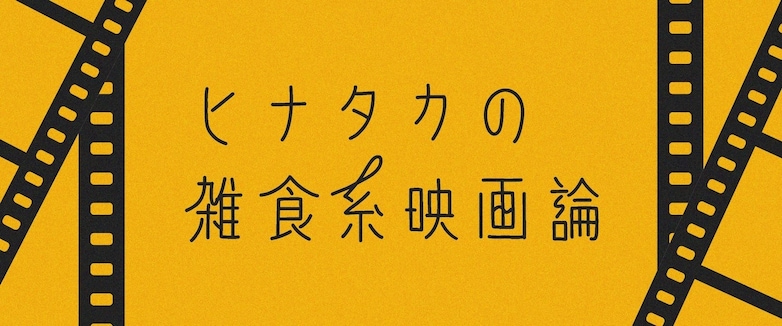3:女性のテクニカル・ディレクターの存在も重要だった
ブラッド・ピット演じる主人公をはじめ、主要キャラクターがいずれも特徴的で覚えやすく、役割が分かりやすいというのも本作の長所でしょう。下記にプレス資料から引用します。いわゆる「チームもの」にもなっているわけですが、中でも女性のテクニカル・ディレクターの存在は重要です。ケイトというキャラクターは、実際に「F1®」界で活躍する女性エンジニアたちからも着想を得たそうで、彼女を演じたケリー・コンドンは以下のようにも語っています。ソニー(ブラッド・ピット)声:堀内賢雄 かつて世界を震わせた伝説の元F1®レーサー。 最下位に低迷するF1®チームを救うため現役復帰を果たす。
ジョシュア(ダムソン・イドリス):声: 森本慎太郎(SixTONES) 才能溢れるが自信過剰なルーキー。常識破りなソニーに反発を繰り返す。
ケイト(ケリー・コンドン)声:佐古真弓 ピットクルーのリーダー。ソニーたちのマシン開発担当。 チームのために最強マシンの開発に挑むことに――
ルーベン(ハビエル・バルデム)声:大塚明夫 最下位に低迷するF1®チームのオーナー。 ソニーの旧友でチーム再起の希望をソニーに託すが…
そのケイトの背景について、劇中でそれほど大きく描かれるわけではありませんが、男性中心の価値観が根強く残る社会の中で、「私は私」という揺るぎないアイデンティティーを貫いている一方で、賭けの世界にはどこか不安を感じているようにも見受けられます。ケイトは本気でレースを愛しているんだと思う。だって、F1®って本当に消耗する世界だから。1年のうち9か月は世界中を飛び回っているし、女性が少ない。だからこそ、“わたしには無理だ”って思っている人たちを見返したいっていう気持ちが、彼女にはあるんじゃないかな。ところが、どれだけ準備をしても、タイヤのことや気温のことを考えても、最終的にはサイコロを振るしかない。そういう“賭け”の感覚に中毒性があるんだと思う。それが、この過酷なスケジュールにもかかわらず、F1®の世界に魅せられてしまう理由なんだと思うの。

また、コシンスキー監督にとって映画の出発点となったアイデアの1つが「F1®」のドキュメンタリー『フォーミュラ1:栄光のグランプリ』であり、その第1シーズン「有名なドライバーやトップチームではなく、グリッドの後方にいるチームに焦点が当てられていたこと」に感銘を受けたのだとか。
そのこともあって、やはりチームとしての奮闘もまた重要な内容となっているのです。
4:事前に把握しておくといい用語は?
劇中では冒頭で「ル・マン24時間レース」の概要や「F1®」の基本的なルールが簡潔に説明されるため、事前に予習しておく必要はほとんどないでしょう。それでも、ここでは公式資料である「ソニーの作戦がもっと面白くなる!F1®ルール解説~入門編~」から、ネタバレにならない範囲で知ってほしい用語やルールを、一部抜粋・引用、また追記もしつつまとめてみます。
「DRS(ドラッグ・リダクション・システム)」……リアウィングという車の“羽”の一部が開いて、空気抵抗が減りスピードがアップする仕組み。前の車に1秒以内まで近づいたときだけ、決められた直線区間で使えるというルールとなっている。
「ERS(エネルギー回生システム)」……F1®カーは、ガソリンだけでなく電気も使って加速する。車がブレーキをかけるときに発生する熱や運動エネルギーを電気に変えてバッテリーにため、それを加速のときに使う。
「セーフティカー(SC)」……コースに事故車や破片があるとき、全車を安全にゆっくり走らせるための車。全車はその後ろで隊列を組んで走り、危険がなくなれば再スタートする。このとき、タイヤ交換をするチームも多い。
「赤旗(レッドフラッグ)」……レースを一時中断するルール。コースが完全に危険な状態(大事故・大雨など)のときに出され、全車がピットに戻って待機する。その後、安全が確認されると、再びスタートが行われる。なお、黄旗(イエローフラッグ) はコース脇やコースの一部に危険箇所がある時に出される。
「青旗(ブルーフラッグ)」……トップを走る車にラップ(周回)遅れになりそうな車は、道をゆずるルール。青旗が振られたら、速い車を妨げないように走るのがマナー。これを無視するとペナルティが課せられる。
タイヤの戦略について……F1®ではタイヤに「ソフト・ミディアム・ハード」の3種類があり、それぞれに「ソフト(赤):速いけどすぐ減る」「ミディアム(黄色):バランスが良い」「ハード(白):長持ちするけどちょっと遅い」という特徴がある。
ピットの戦略について……ピットはサーキットに設けられている車の整備を行う施設。「どのタイヤに替えるか?」だけでなく、「いつ入るか?」「セーフティカーや赤旗とタイミングを合わせるか?」も重要な場面であり、チームの「頭脳戦」の場面ともいえる。
やはり、「とにかく速ければOK」というわけでなく、やはり「戦略」も大切で、それもまたモータースポーツの面白さでもあると再確認できるはずです。
5:レースの世界に限らない「贖罪」の物語
コシンスキー監督は「これは、贖罪(しょくざい)の物語。レースファンでなくても楽しめる」と語り、以下のようにも続けています。まさにその通りで、本作で描かれたのは、かつては周りの期待に応えられなかった男が「もう一度信頼を取り戻そうとする」物語です。若い頃のソニーには大きな期待がかかっていたが、結果はついてこなかった。それが彼の人生を狂わせた。でも、彼は自分なりのやり方で道を切り開いた。この物語は、レースの知識があろうがなかろうが、多くの人が共感できる話なんだ。
主人公のソニーはちょっとイヤなやつだと前述してしまいましたが、それはあくまでも表向きの振る舞いに限ったことであり、実は女性のテクニカル・ディレクターであるケイトにも、自信過剰なルーキーであるジョシュアにも、誠実に向き合っていたのではないかと、後から思えるところもあります。はたまた、型破りな作戦も、チームを勝たせるための、彼なりの最善の方法だったのではないか、とも考えられるでしょう。

この記事の筆者:ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW(ニュー)」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。