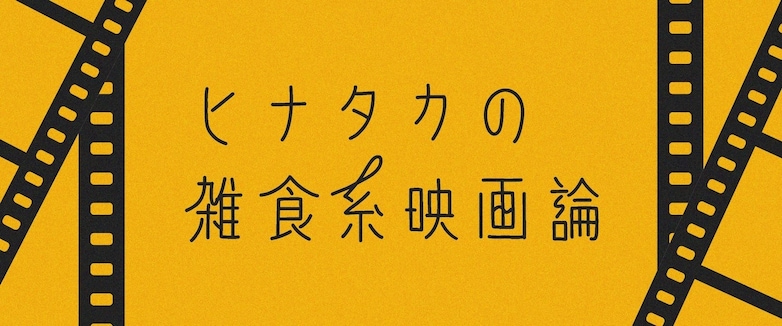戦争を経験した人たちが存命である最後の時代かもしれない
これらの戦中・戦後の映画が、2023年の今に送り出された理由および意義は、第2次世界大戦を経験した方がご存命である最後の時代だから、ということも大きいと思います。『窓ぎわのトットちゃん』の物語の始まりで小学1年生だったトットちゃんこと黒柳徹子は、今では90歳で、現役で活躍されています。この映画を見て涙を浮かべ、内容を振り返る動画も公開されていました。
これからは、戦中・戦後を経験した人は、どんどんいなくなってしまいます。だからこそ、これらの映画が残り続け、後世にも伝えられる意義はとてつもなく大きいといえるでしょう。戦争を経験したご存命の人にも、その経験を聞いたという人にも、『窓ぎわのトットちゃん』をはじめ、これらの映画を見ていただきたいです。
戦争がなくならない今の時代だからこそ
八鍬新之介監督が『窓ぎわのトットちゃん』の企画に着手したのは2016年。その年はシリアの内戦で化学兵器によって子どもが犠牲になり、障がい者施設での殺傷事件など暗い出来事が起こったため、子どもたちが生きる未来のため、社会に貢献できることはないだろうかと考えて、アニメ映画化を決意したのだそうです。今では言うまでもなく、ロシアによるウクライナへの侵攻、イスラエルによるガザ地区侵攻と、痛ましいという言葉でも足りない戦争が起こっており、多数の子どもが亡くなり、偏見や差別による分断がさらに起こっています。このような世界で、『窓ぎわのトットちゃん』の劇中で描かれた「戦争にも奪わせないもの」は大きな希望になり得るのではないでしょうか。
子どもに背負わせてはならないもの
さらに、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は戦後に弱者を踏みにじる搾取構造を描いた作品であり、そのような世界で「加害者側」になる危険性も示された作品でした。不安定な世の中で「長いものに巻かれろ」とばかりに強者側につくのではなく、「人間」としての誇りや善性は絶対に失ってはならないことも、今一度確かめられるでしょう。『君たちはどう生きるか』は戦争そのものをメインに捉えているわけではなく、あくまで物語の背景かつ、主人公の心の揺れ動きに関わっているものでした。でも、だからこそ、戦争で不安定になった世界で生きる人たちが、家族への愛情を確かめる物語としても成り立っています。
さらに上記の6作すべてで、子どもが物語に関わっています。2023年の今、ご存命の方も言うまでもなく当時は子どもでしたし、(特に『ほかげ』で)「この戦争による負の遺産を子どもには受け継がせてはならない」という、作り手のメッセージが伝わりました。映画本編を見てそのメッセージを受け取れば、戦争について深く考える大きな原動力にもなるはずです。
この記事の筆者:ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「CINEMAS+」「女子SPA!」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。