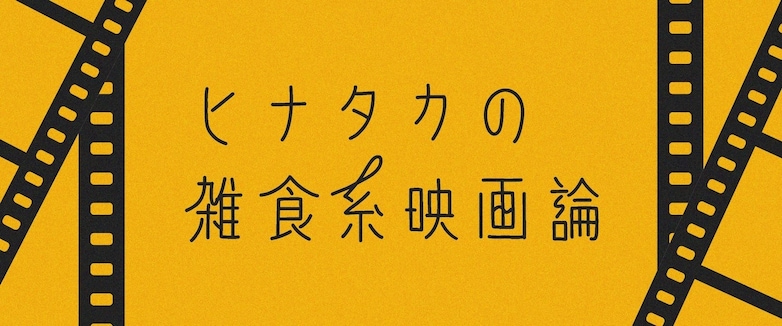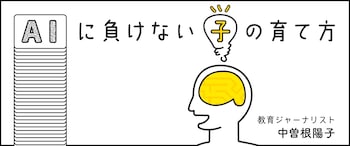「登場人物が知らないことを観客は知っている」がもたらす効果は
そもそも、「登場人物が知らないことを観客が知っている」というのは、物語を紡ぐ作品における重要なテクニックです。例えば、『サイコ』などで知られるアルフレッド・ヒッチコック監督は、「テーブルの下に隠された爆弾」を例に取り、その存在を登場人物は知らないが、観客だけが知っている場合はサプライズではなくサスペンスとなり、緊張感を持って観客に注視される効果を生むと語っています。
「観客が登場人物よりも多くの情報を持っている状況」を指す「劇的アイロニー」という言葉もあります。それによって、単なるサスペンスだけでなく、登場人物たちの勘違いが客観的に見る観客には思わず笑ってしまうようなコメディーとなり、すれ違いは心をくすぐるようなもどかしさと切なさを伴うドラマにもなっていきます。
そして、今回の『鬼滅の刃 無限城編』では、人間と鬼それぞれの長い回想と、その交わらなさを示すことで、両者の心境を把握しているのは観客のみという状況が作り出され、ある種の「神の視点」がほかの映像作品よりも極まっています。ここまでくると、もはや単に「冗長な演出」と片付けることはできないのではないか、と感じるのです。
前述してきた猗窩座の過去に限らず、実際の死闘を知らない炭治郎が、カラスからの伝言で胡蝶しのぶの死を知ったこと。しのぶが嫌悪感を抱いた以上の歪んだ思想が、鬼の童磨(どうま)にあること。それぞれで、観客は登場人物よりも多くの複雑な感情が入り交じったまま、物語を追うことになるのですから。 「全てを知っていて、こう感じられるのは観客だけ」という、ある種の特別な立場があるからこそ、『鬼滅の刃 無限城編』は、ここまでエモーショナルに描かれているのだと言えるでしょう。
余談ですが、猗窩座の「何ともまあ惨めで、滑稽で、つまらない話だ」という言葉のように、登場人物のセリフが物語を知る観客には「そうじゃない」と響くことで深い感動を呼ぶ作品に、実写映画『アイアムアヒーロー』(R15+指定)のラストシーンも挙げられます。こちらも、ぜひご覧になってみてほしいです。
毒を入れた犯人もはっきりする「収めきれなかった物語」もあった
猗窩座の物語は、映画で回想シーンを丁寧に、時間をかけて描いたからこそ、深い感動を呼んでいるとも言えるでしょう。一方で、実は原作者である吾峠呼世晴は「長くなるため本編に入れられなかったお話があった」ことを語っており、そちらでは「毒を入れた犯人」も判明しています。原作漫画の第18巻のおまけページの「設定こぼれ話」として記されていたのは、非常に乱暴で横柄な「隣の道場にいた後取り息子」の物語でした。焚き付ける門下生の声もあって井戸に毒を入れたのが彼であり、狛治が惨殺した67人の中にも彼がいたのだと明言されているのです。
この物語が劇中で描かれたとしても、「毒を使ってでも勝ちたかった」という弱者の視点が加わることで、猗窩座が結果的に嫌悪するものが浮き彫りになり、より象徴的な意味合いを持つ内容になることでしょう。
しかし、現状の内容では、観客もまた「毒を入れた犯人を知らない」状態です。猗窩座と同様に観客も全てを知り得ないからこそ、殺戮を行い、復讐(ふくしゅう)を遂げられたかも分からない、猗窩座の「空虚さ」に同調しやすくする効果も生んでいるとも考えられます。
結論として、『鬼滅の刃 無限城編』において「登場人物が知らないことを観客だけが知っている」という構図は、観客の感情を大きく揺さぶるだけでなく、「弱者を虐げることで強者を目指す」ことの虚しさや愚かさを際立たせる働きも担っており、それは現代の多くの人々に届いてほしい誠実なメッセージをより力強く伝える要素となっているのです。
この記事の筆者:ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW(ニュー)」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。