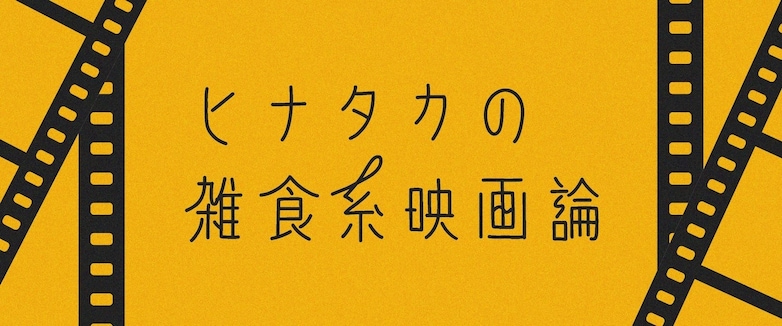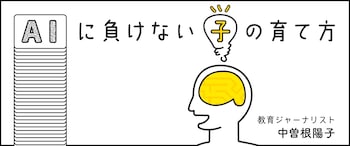猗窩座と炭治郎の主張の「平行線」
本作で最大の見せ場となるのは、竈門炭治郎(と冨岡義勇)と猗窩座の死闘です。この2人に限らず、『鬼滅の刃』という作品において、ほとんどの「鬼」と「人間」の表向きの主張は“平行線”のままで、交わることはありません。 例えば、猗窩座の「弱者には虫酸(むしず)が走る、反吐が出る。淘汰されるのは自然の摂理に他ならない」といった主張に対し、炭治郎は「強い者は弱い者を助け守る。そして弱い者は強くなり、また自分より弱い者を助け守る。これが自然の摂理だ」と真っ向から否定します。一方で、炭治郎の主張は、かつて猗窩座が狛治(はくじ)という名前の人間だった頃、師匠である慶蔵(けいぞう)から学んでいた、「何をするにも初めは皆、赤ん坊だ。周りから手助けされて覚えていくものだ」という主張にかなり近いものでした。
そして、記憶を失いながらも少しずつ思い出しつつある猗窩座が、このときの炭治郎に対して強い不快感を覚えたのはなぜか。後に観客には、その理由が「つまらない過去を思い出させるから」だと示されます。さらに言えば、「本当は分かっているのに、そうできなかったから」という後悔ゆえだと、明確に伝わるようになっているのです。
「つまらない話」だけではないと思える理由
劇中の炭治郎が最後まで知ることができなかったのは、猗窩座が「狛治だった時の出来事」です。彼は病弱な少女・恋雪(こゆき)の看病を続けており、自身の父もまた病気だったこともあって「病で苦しむ人間は何故いつも謝るのか」「一番苦しいのは本人のはずなのに」と、弱っている者の「自己否定」をいぶかしく思うことができる、優しい人間だったはずなのです。 しかし、誰かが井戸に毒を入れたことで、慶蔵も、夫婦(めおと)になる約束をしていた恋雪も殺されてしまい、狛治は「俺は誰よりも強くなって一生あなたを守ります」という心からの言葉でさえも、「口先ばかりで何一つ成し遂げられなかった」と後悔します。さらには隣の剣術道場の67人を惨殺し、鬼舞辻無惨(きぶつじむざん)に鬼に変えられようとするその時に「もう…どうでもいい…すべてが…」と口にしていました。結果として、守るべきものは何1つ残らず、ただ100年以上も無意味な殺戮(さつりく)を繰り返してきたことを、猗窩座は「まったくもって惨めで、滑稽で、くだらない話だ」と振り返ることになるのです。
しかし、観客にとっての猗窩座の物語は、それらの言葉だけにとどまりません。前述した弱者を否定する勝手な持論は、かつて「正々堂々と戦わずに井戸に毒を入れた者」に向けた言葉でもある一方で、「守る拳」であったはずの自分の力で多くの人を惨殺した猗窩座自身を指していることも読み取れます。
そして、結局は自己否定をせざるを得なかった悲しさと、たとえ想像の中でも、最後に恋雪に「お帰りなさい、あなた」と迎えられたこと……それぞれが胸を打ちます。「ただ惨めで、滑稽で、つまらない話」だけではないと観客が思えるのは、猗窩座という「弱者を愛することができるはずの人間」の未来が踏みにじられてしまった悲劇と、罪を犯し続けた彼が最後の最後にわずかでも救われたことを、知るに至ったためです。
そして、『鬼滅』という作品において、鬼は不老不死であり、かつ人間を喰らうという、絶対的な「強者」です。現実には存在しない鬼を通じて、『鬼滅の刃』は、一方的に弱者を踏みにじる強者がいかに間違っているかを徹底的に描いているとも言えるでしょう。
そして、絶対的な強者である鬼へと変わってしまったからこそ、弱者である人間との価値観に迎合することはなくなり、両者の回想が全く交わらないことにも、必然性があると思えるのです。