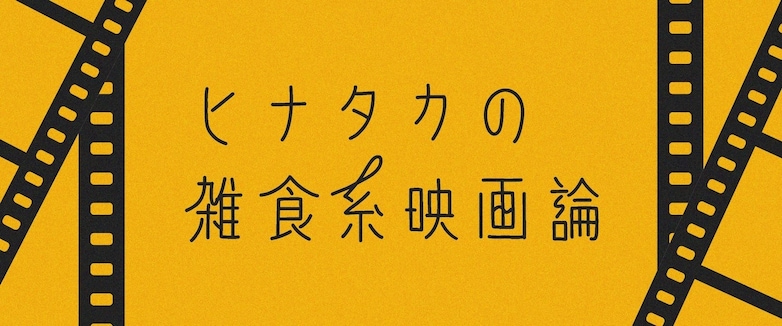3:ウィリアムス自身が自分を猿だと語っていた
そうした1人の人間の葛藤や矛盾を描きながら、それほどセンチメンタルにはならない、むしろ「いっそスガスガしく」見られるところが、本作の大きな特徴かつ魅力でもあります。その理由の筆頭が、やはり主人公を「猿」として描いてることです。何しろ、猿は人間に近い知能の高い動物である一方で、「頭が悪い」「浅薄」といった蔑称のように用いられることもあります。劇中でウィリアムス自身が猿として描かれることも、「しょせん自分は猿のよう」だと自虐しているようにも思えます。

主人公を猿として描くアイデアも、実際のウィリアムスが「自身を猿と例えていたから」だったりもします。グレイシー監督は彼に会うたびに「僕は猿のように後ろで踊っている」「僕は完全に心ここにあらずだったのに、まるで猿のようにパフォーマンスするためにステージに引っ張り上げられた」などと口にするため、しばらくして「それならばいっそのこと、映画の中のロブを猿として描くのがいいのではないか? 」と思ったのだとか。
そうした浅薄さや自虐が劇中の猿には確実に込められている一方で、逆説的にウィリアムスというその人の「本質」に触れるような感覚にもなるのも重要でした。何しろスクリーンに映し出されるのは、ある種の動物的な本能、あるいは「無邪気」ゆえの言動をする猿=ウィリアムスの姿であり、だからこそ彼が深く傷つき絶望する心境がギャップとなり、人間の姿よりもより切実で強く気持ちを揺れ動かされる感覚があったのです。
また、グレイシー監督は、猿の姿でウィリアムを描いたことについて、特別映像では「周りからではなく君自身の視点で描く方法」「君の実像を描く最高の方法」とも語っています。つまり、ウィリアム自身の視点と実像が、彼を猿として観ている観客と一致している。これこそが、主人公を猿にした最大の意義といえるかもしれません。
ちなみに、劇中でのウィリアムスによるナレーションの大部分は、もともとは映画のためのものではなく、1年半をかけて録音した複数のインタビューから取られたものだったのだとか。ウィリアムスの演奏をモーションキャプチャーをして、その表情や物腰までをも忠実に参照し、猿のキャラクターに落とし込んだ(実際に演じたのは俳優のジョノ・デイビス)ことに注目なのはもちろん、そのナレーションもまた「本物」なのです。
4:賛否もあった『グレイテスト・ショーマン』と本質は似ている?
グレイシー監督の『グレイテスト・ショーマン』は絶賛される一方で、物語および主人公像には賛否もありました。そちらは「地上最高のショーマン」とも呼ばれた実在の興行師であるP・T・バーナムを描いた作品であり、彼は客観的には「フリークスと呼ばれる人たちを利用して金儲けをした山師」というネガティブな捉え方もできるからです。
とはいえ、劇中で彼を絶対的に正しい存在としているわけではなく、「利己的な面もあるし間違った言動もしているが、彼に才能を見出された人たちが救われてもいたことも事実」だとしっかり描かれてはいました。しかし、きらびやかなパフォーマンスも相まって、“良い話”のように見えてしまうバランスに居心地の悪さを感じた人は一定数いたようです。
今回の『ベター・マン』では、ある意味で『グレイテスト・ショーマン』にも存在していた「主人公の正しくなさ」を、かなり強調する形で描いています。その意味ではグレイシー監督の作家性は一貫していますし、実は『グレイテスト・ショーマン』と『ベター・マン』は似た話といっても過言ではありません。

ちなみに、『グレイテスト・ショーマン』の主演であるヒュー・ジャックマンは、自身の役のバーナムに言及する時はいつも「ロビー・ウィリアムスのように」と表現していたそうです。スタッフ全員の間でも、「ショーマンシップ」「自信に満ちた態度」「音楽性」「パフォーマンス」において、必ずロビー・ウィリアムスを引き合いに出すというのがジョークにもなっていたのだとか。
ヒュー・ジャックマンにとって、現実のウィリアムスが、バーナムを演じる指針になっていたことを鑑みると、より『グレイテスト・ショーマン』と『ベター・マン』はある種の「姉妹作」のように、面白く見られるかもしれません。