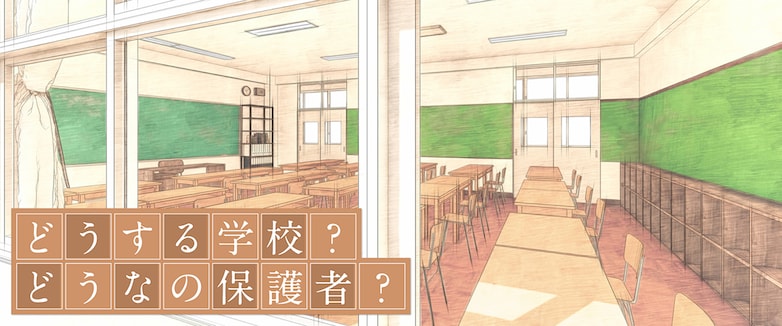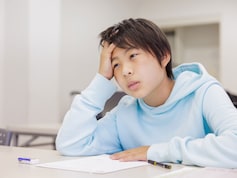通学方法は学校や近所の人が決めることなのか
先回りして、1点だけ。時々「海外では、子どもの学校送迎は親がやるのが当たり前。日本だって同様にすべき」といった意見が聞かれますが、ここは治安の良さで知られる日本です。状況の違う国を基準にしなくていいと思うのです。それにそもそも、登下校の方法は、保護者が決めることではないでしょうか。1人で通わせたければそうすればいいし、学校が遠いから、あるいは途中に危ない箇所があるからほかの子と一緒に通わせたい、自分が付き添いたいと思うなら、そうすればいいこと。それを一律に、学校や近所の人が「こうやって通え」と決めることにムリがあるのでは。
登校班の見守りも、スクールバスの同乗も、昭和の時代に「多くの母親が専業主婦である前提」でつくられてきたルールです。「今の時代」を前提に慣習やルールを見直さないと、これからさらに困る人が増えていくことは免れません。
この記事の執筆者:大塚 玲子 プロフィール
ノンフィクションライター。主なテーマは「PTAなど保護者と学校の関係」と「いろんな形の家族」。著書は『さよなら、理不尽PTA!』『ルポ 定形外家族』『PTAをけっこうラクにたのしくする本』『オトナ婚です、わたしたち』『PTAでもPTAでなくてもいいんだけど、保護者と学校がこれから何をしたらいいか考えた』ほか。ひとり親。定形外かぞく(家族のダイバーシティ)代表。