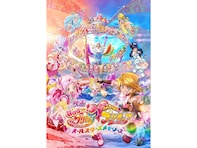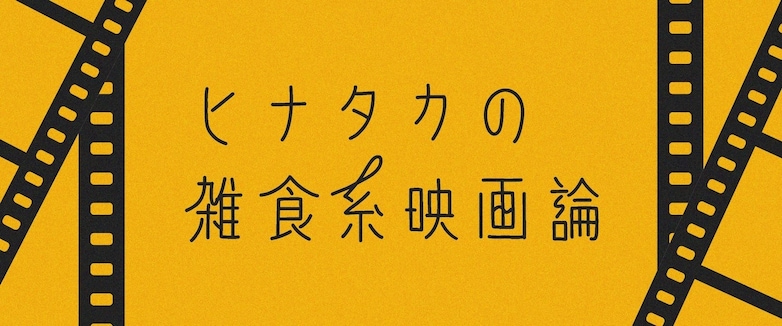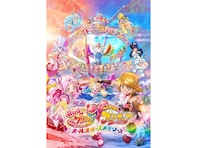3:「神聖」な舞台で「変えられるもの」「変えられないもの」も肯定できる
さらに、劇中では、アメリカの神学者の「ニーバーの祈り」が引用されています。これらの言葉は、そのまま3人それぞれの選択に当てはまりますし、特に「変えるだけの勇気」は、やはり「好き」という本音を表に出すことにもつながるのだと、物語を振り返って思うことができるでしょう。「変えることのできないものについて、それを受け入れるだけの心の平穏をお与え下さい」
「変えることのできるものについては、変えるだけの勇気をお与え下さい」
「変えることのできるものと、できないものとを、区別できる知恵をお与え下さい」

シスター日吉子が終盤に明かすとある秘密も含めて、「変えられるもの」「変えられないもの」の両方を、あるいは神という存在そのものさえも肯定するようにも思えたのです。
4:ノベライズ版やコミック版で補完もできるけど、映画で描かれないことにも意義がある
ストレスを与えない内容は意図的とはいえ、劇中で「描かれない」ことが多いのも事実で、そのためにモヤモヤを抱えてしまう人もいるでしょう。その「補完」がしたいのであれば、ぜひノベライズ版やコミカライズ版を読んでみることをおすすめします。
さらに、コミカライズ版では、古書店でトツ子が「私たちのバンドに入りませんか」と言うその瞬間に至るまでの、きみとルイそれぞれの心理が描かれています。トツ子の提案が、2人にとってどれほどうれしかったのかが、よりはっきりと分かるでしょう。

でも、それでもいいのだと思います。寮のベッドの中で、トツ子に「(仮病という)うそをつかせちゃった」と罪悪感を口にするきみに対して、「私、今すごく楽しいし、うれしいよ。あとね、きみちゃんが言いたくないことは聞かないよ。でもおばあちゃんには一番に話したほうがいいと思う」と言ってくれたように、主人公のトツ子にとって、あるいは彼女の目線で物語を追う我々観客にとっては、「知らなくてもいいこと」なのですから。
その他でも、劇中のほとんどはトツ子の主観で物語が進んでおり、例外となるのはきみが祖母に、ルイが母親に「隠していたこと」をそれぞれ打ち明けるシーンと、その他のわずかな場面のみです。そのトツ子が、今まで見えなかった「自分の色」をどんな時に見つけることができるのかという点にも、ぜひ注目してください。