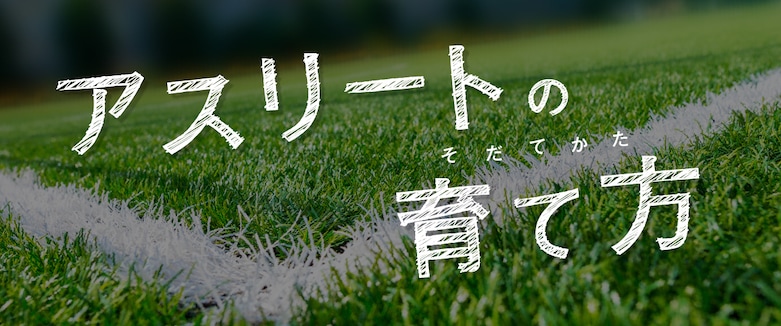「ずば抜けたもの」を見つけて、伸ばしてあげればいい
では今の時代、どのような子育てをすれば、プロの世界で成功するようなトップアスリートは育つのか。「正解は1つじゃないと思います。周りの環境やタイミング、もちろん子どもの性格も関係してくるでしょう。ただ、親の思い込みで勝手に子どもの能力を評価してしまうのは、特に過大評価をして過度なプレッシャーを与えてしまうのは、ちょっと違うんじゃないかと。トップアスリートになれるかどうかは、結局のところ子どもの能力次第であって、親の能力ではないんですから。
でも、いろんなアスリートの方と話をしていると、やはり何か特化した武器を持っている人が多いなって気付きますね。それは運動能力や技術に限らず、発想の豊かさでも強い精神力でもいんです。何か1つずば抜けたものがある人は、きっとどんな世界でも成功できるんじゃないかと思うんです。
だから、できないことをできるようにすることも大事ですけど、それ以上にその子の得意な分野、突出した武器を見つけてあげて、それを楽しみながら伸ばしていけるような環境を与えてあげること。そんなサポートが、僕は1番いいのかなって思いますね」
子どもには子どもの人生、時代がある
当然ながら、昭和の子育てと令和の子育ては、考え方の根本からして違う。それぞれに良い点もあれば、悪い点もあるだろう。無論、時代におもねる必要はない。しかし大切なのは、そうした時代の変化を理解し、受け入れて、今を生きる子どもたちと向き合えるかどうかではないか。城も、子育ての難しさをこう語っている。「以前、娘に『それはパパの時代の考え方でしょ』って言われて、ハッとしたことがあったんです。僕たち親は、無意識のうちに自分がこれまで歩んできた人生の枠組みで物事を考えて、そこに子どもたちをはめ込もうとしてしまう。でも、彼らには彼らの人生があって、彼らが生きている今の時代があるんです。それにそぐわないような指導や教育って、もう要らないんですよ。まあそう言いながら、僕も自問自答していますけどね(笑)」
>>>【前編】3万円を手渡し「頑張って来いよ」。破天荒すぎる父が中学生だった城彰二に課した極貧サバイバル生活
城彰二(じょう・しょうじ) プロフィール

この記事の執筆者:吉田 治良 プロフィール
1967年生まれ。法政大学を卒業後、ファッション誌の編集者を経て、『サッカーダイジェスト』編集部へ。2000年から約10年にわたって『ワールドサッカーダイジェスト』の編集長を務める。2017年に独立。現在はフリーのライター/編集者。