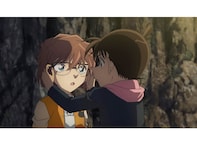特徴的なのは、言わずと知れた宮沢賢治を「ダメ息子」として描いていることと、だからこそ「親バカ」な父親の息子への愛情も伝わる家族の物語にもなっていることでした。
「どうしてもこの2人でやりたかった」役所広司×菅田将暉の演技に注目
そして、映画の最大の魅力は、その親バカを役所広司、ダメ息子を菅田将暉が完璧に演じ切っていることだと断言します。成島出監督は原作にほれ込んだ上で「どうしてもこの2人でやりたかった」と語っており、なるほど映画を観れば、このキャスティングを“絶対条件”にしたことに大納得でした。その理由を記します。
「親バカ」がすぎる役所広司のチャーミングさ
映画で描かれるのは、宮沢賢治が誕生した明治29年(1896年)から、大正を駆け抜けて、昭和10年(1935年)までの約40年にわたる物語。まず誰もが印象に残るのは、翌年に小学校入学を控えた賢治が赤痢(せきり)にかかってしまった時のこと。そこで父の政次郎は「賢治の世話は私がする!」と宣言するのです。
「質屋の仕事はどうするんだ」「男子のやることではない」と、田中泯演じる祖父・喜助に怒られても、「医者になど任せられるか!」と病院に駆けつけて、かいがいしく笑顔で世話をするのでした。一連の行動を見た祖父が口にしたのは「おめぇは、父でありすぎる」という、褒め言葉というよりもあきれ果てて出た言葉だったのです。
賢治が成長してからは、後述するように“めちゃくちゃな言動”をする賢治を叱りつける場面も多かったのですが、森七菜演じる妹のトシに良い感じの言葉を並べておだてられると、その言葉を賢治にそのまま言うので、笑ってしまいました。頑固のようで実は素直なところもある父・政次郎のことを(ちょっと引きつつも)誰もが好きになってしまうはずです。

そんな“親バカ”に役所広司がハマる理由は、本人にチャーミングさがあり、かつ大真面目な様もコメディーとしてクスクスと笑える場面にできる、役者としての力があるからでしょう。加えて、作品によっては鬼気迫るような重い役も演じられる人なので、激しく息子の賢治を叱りつける様に、良い意味でのギャップと説得力があります。これらの要素を兼ね備えているのが役所広司だと言われれば、なるほど「他の人は考えられない」と思えるほどだったのです。
>次のページ:ピュアでブレない宮沢賢治を菅田将暉が演じる「説得力」