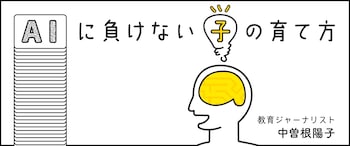親は、子どもにとって一番の頼れる存在でいたいもの。しかし、どんな親が子どもにとっての「頼れる存在」なのかをはっきり答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。
その1つのヒントとなるのが、小学校教師として日々子どもたちに向き合っている松下隼司さんが提唱する「教師五者論」。子どもにとって必要な役割を、身近な大人が演じるという考え方は、学校の先生だけではなく子育て中のパパママにとっても参考になります。
「教師五者論」の考え方を、松下さんの著書『先生を続けるための「演じる」仕事術』から一部抜粋して紹介します。
親子の関係にも通ずる、「1人5役」の理論とは?

この「教師は五者たれ」の話を聞いたとき、正直、自分には五者も無理や……と思いました。教師は子どもに教えるために、“学者”のように学び続けなさい。
教師は、“医者”のように子どもを診なさい。子どものしんどさに気づいて、それを解消できるようになりなさい。保健室の先生みたいにケガの手当をしなさいって意味じゃないよ。
教師は、“役者”のように子どもを魅了する授業や対応をしなさい。教師自身が演じるだけでなく、子どもの良さを引き立てるような演出力も身に付けなさい。教師が目立ってばかりでは、だめだよ。子どもが主役になるようにね。
教師は、“易者(占い師)”のように、子どもの将来を見通した指導をしなさい。本当に占うんじゃないよ。
教師は、“芸者”のように、楽しい時間をつくりなさい。子どもが「学校って楽しい」 と思えるようにしなさい。
私にこの話をしてくださったその超ベテランの先生も、「こんな話をしている自分も、まだできていないけどね」と言っていました。(なおさら私なんかには無理だ、分かりやすい授業をするだけでも難しいのに……と重荷に感じました)
子どもと接するときは、自分の中のロールモデルになりきる!
そこで、私のように劣等感がある方でも、楽しく「教師五者論」を実践する工夫を紹介します。(「教師五者論」を実践するための工夫は、教職以外の仕事をする方にも役立 つと思います)それは、“医者”などの職業名でなく、具体的なイメージ像をもつのです。実在する人でなくても、漫画やアニメ、ドラマの登場人物でも構いません。自分が好きな人、憧れる人を思い浮かべて、その人になりきってみるのです。
あなたが教師五者論で、それぞれ思い浮かぶ人は誰でしょうか?
次は、私にとっての〝五者の理想のイメージ像〟です。【学者】→
【医者】→
【役者】→
【易者】→
【芸者】→
知らない人物ばかりでしたら、すみません。でも、自分にとっての五者のモデルはそれぞれ誰かなと考えることが役作りには大切ですし、なにより楽しいです。【学者】→ボクシング漫画『はじめの一歩』の主人公、幕ノ内一歩。トレーナーとして人に教える立場にいる。ボクシングを現役時代よりも学んでいる。
【医者】→医療漫画『リエゾン』に登場する主人公、佐山卓。児童精神科・佐山クリニック院長。
【役者】→ベテラン俳優、近藤芳正さん。
【易者】→山岳漫画『岳』の主人公、山崎三歩。山岳救助隊として、山で遭難した人を「大丈夫! 助かる!」と励ましながら救助する。
【芸者】→NHK Eテレ「みいつけた!」のオフロスキー(小林顕作さん)
教師の仕事は、指導力・知識力・判断力・受容力・説得力・診立て力・共感力・演技力・ 表現力・演出力・予見力・想像力・創造力など、たくさんの能力が求められます。
さらに、五者に加えて「忍者たれ」(忍耐力)、「指揮者たれ」(統率力)、「テクノマスターたれ」(ICT機器を使いこなす能力)、「ペアレントハーモニーたれ」(保護者との関係を調和的に築く能力)と、求められる姿が多くあります。
アシュラマンというキャラクターをご存じでしょうか? 1979年に連載が始まり、2024年にリバイバルしてアニメ化もされている漫画『キン肉マン』の登場人物です。
アシュラマンは、3つの顔を持っています。そして、状況に適した顔(特性)にチェンジして、敵と闘います。私もアシュラマンが顔をチェンジする動作を真似して、その時々の状況に応じて五者(プラスα)を演じ分けています。具体的なイメージ像をもって真似していると、だんだん板についていきますよ。 松下隼司さん
大阪府公立小学校教諭。令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。令和6年版教科書編集委員。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクール文部科学大臣賞、第69回(2020年度)読売教育賞 健康・体力づくり部門優秀賞などの受賞歴を持つ。新刊『先生を続けるための『演じる』仕事術』(かもがわ出版、2025年8月19日発売)など著書多数。voicyで『しくじり先生の「今日の失敗」』を発信中。