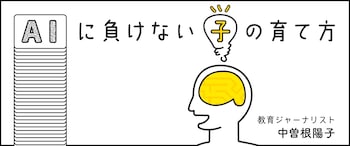そんな理想的な教育は、本当に実現できるのでしょうか?
多くの親御さんが抱く疑問に対し、1つの答えを示してくれるのが、千葉県にある渋谷教育学園幕張中学校・高等学校(通称「渋幕」)です。
東大合格者数14年連続全国トップ10入りという輝かしい進学実績で知られる渋幕ですが、その教育の真髄は単なる受験指導にはありません。チャイムが鳴らず、校則もほとんどない、生徒の自主性を徹底的に重んじる「自由な校風」の中で、子どもたちは自らの好奇心にしたがって学び続けています。
しかし、この「自由」は決してラクなものではないはずです。自分で考え、決断し、行動しなければ何も進まない環境で、生徒たちはどのようにして自立した学習者へと成長していくのでしょうか。教育ライターが見た、渋幕の教育現場の実像を紹介します。
※この記事は、『渋幕だけが知っている「勉強しなさい!」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』(佐藤智 著)から一部抜粋したものです。
全国屈指の進学校が進学実績より大事にしていること
・チャイムが鳴らない。・遠足や修学旅行は現地集合・現地解散。
・校則が(ほとんど)ない。
・(ほとんど)先生から指導されない。
・部活動や同好会を生徒が作れる。
・行事への参画度合いは自分次第。
渋幕の卒業生に学校の特徴を尋ねると、以上のような回答が返ってきました。
生徒の自主性を重んじ、やりたいことができ、教師は「指導者」ではなく「相談相手」。たしかに実態として、「自由な校風」というものがあったのです。
本書の取材のため、私は何度も渋幕へ足を運び、先生方、生徒たち、卒業生のみなさんのお話を聞きました。そこでよくわかったのが、「学校でのあらゆる場面に教育目標が染み出している」ということ。
「自由な校風」も「グローバルな教育」も言葉でいうのは簡単です。
しかし、それを真に実現するには、覚悟と一貫した姿勢が必要です。渋幕の先生はひとりひとりの生徒を見つめ、ときには葛藤したり不安になったりしながら、実現に向けて歩んでいました。
「自分で決断していく時代」への対応力が自然に身につく環境
お父さんお母さんも、近年「主体的な学び」や「自立」といったキーワードが教育で重視されてきていることはご存じかもしれません。これまでの多くの教育現場においては、教育が「子ども主体」ではなく「(子どものために)管理することが必要」という価値観のもとで成り立ってきました。子どもたちのことを真剣に考えているがゆえに、安全な管理下に置き、手をかけて、転ばぬ先の杖を与え続けてきたのです。
しかし、大人からいわれたことをこなせばいい環境にいれば、多くの子どもは「考えなくてもいいや」「どうせ誰かがやってくれる」と思うようになります。転ばないように地ならしをした道ばかりを歩かせていたら、子どもは過度に失敗を恐れるようになります。
渋幕は、そうした教育から飛び出す場です。渋幕では、自分で考えて、決断し、行動しなければ、何も進みません。
「ここを歩きなさい」と誰からも指示されることはないので、でこぼこの中を歩き、ときには転びながらも、自分だけのオリジナルの道を見つけていくことが求められます。
つまり、渋幕が体現する「自由」は、決してラクな「自由」ではない。自分の心の温度が上がることを敏感に感じ取り、頭をフルに回転させて、自分で動くことが欠かせません。
さらにいえば、個々の自由はときにぶつかり合います。それを調整するのも、生徒自身です。
先生はハラハラしながらも、生徒を粘り強く見守り続けます。答えは決して与えません。