今、日本の小中高校では探究学習が導入されているが、学校現場の多くの先生方が「探究学習のスタートである“問い”が立てられない子が少なくない」という悩みを口にする。
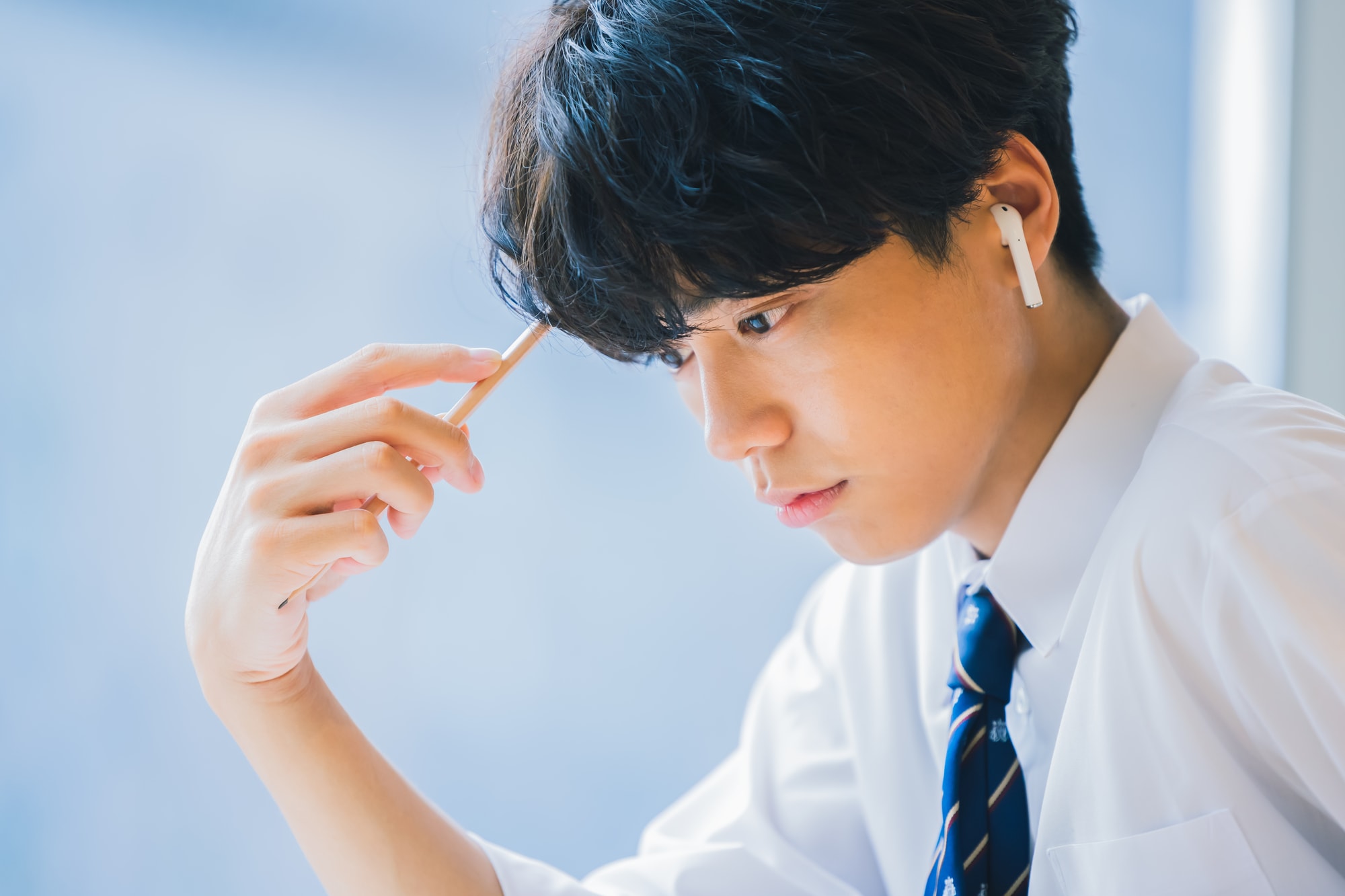
学校現場における探究学習の課題
さまざまな学校の探究学習を支援する株式会社rokuyou(ロクユー)代表の下向依梨さんは、「生徒一人ひとりが、自分の興味関心に基づいたマイプロジェクトに取り組みながら自分と社会への探究を深めていくこと」を目指している。そして、それには「SEL(Social Emotional Learning/社会性と情動の学び)のアプローチが有効だ」という。この学びは「Social(ソーシャル)」と「Emotional(エモーショナル)」の2つの要素から構成されており、自分への気付きを深める力(自己理解力)、自分の感情とうまく付き合う力(自己管理力)、他者への気付きを深める力(共感力)、他者と良好な関係を築く対人関係力(社会スキル)、責任ある意思決定ができる力(意思決定力)の5つの力を養う。
近年、保護者の方は「主体性を育むことが大事」という話をさまざまなところで見聞きするようになったのではないだろうか。ひるがえると、これまでの学校教育では主体性を発揮する教育があまり実践されてこなかった。
そのため、「自身で自己決定する進路選択の場面で混乱したり、社会に出て答えのない問いに向かうことが苦手であったりする。本質的な探究学習では、自分の興味関心に基づいて問いを立て、課題解決のためにアクションをする、主体性を育む教育です」と下向さんは言う。そして、自分の興味関心に気付く自己理解や、他者と協働する際の土台となる共感力をSELのアプローチで耕すことができる。
自分の心へのジャッジメントが邪魔をする
下向さんが代表を務めるrokuyouが拠点を置く沖縄県の高校の授業でこんなことがあったという。SDGsの17の目標から「平和と公正をすべての人に」を選び探究学習を進めていた高校生のグループから「米軍基地について気になる」というつぶやきが聞こえてきたそうだ。「すぐ近くにあるけれど入ったことはないし、なぜ沖縄の人たちと米軍たちはこんなにも交わらないのだろう」と疑問に思ったという。
傍らで彼らを見守っていた下向さんは、「生徒たちが自分の問いをみつけた瞬間だ!」と感じ、それをワークシートに書くよう促した。しかし、その生徒からは「先生に怒られそう。授業っぽくないし」と返事があったという。
「大人や周囲の目を気にして、自分の本当に追いかけたい問いをしまい込んでいる子どもたちはたくさんいます。生徒が本当の心の声を出すためには、教室内の心理的安全性や先生、友達との信頼関係が不可欠です」と下向さんは続ける。












