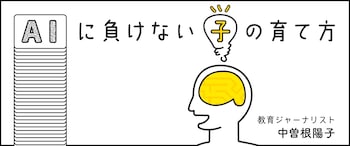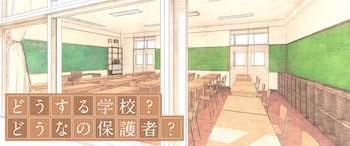今回は、学校現場で「やむを得ず余ってしまった食材のゆくえ」や、実際に行われている食品ロス対策について、食品ロスに詳しいジャーナリストの井出留美さんにお話を聞きました。
学級閉鎖などで発生した、やむを得ない食品ロス……どうしてる?

「学級閉鎖などでやむを得ず余ってしまった食材の扱いは、自治体や学校レベルで異なります。食品の安全性を考慮し、余ったものは全て廃棄するという判断をされている学校もあれば、食品として再利用、もしくはそれ以外の用途として再利用されているという例があります。
具体的な活用方法としては、各地域のフードバンクに食材を提供し、そこからこども食堂や社会福祉協議会などに役立ててもらうという例が多いようです。そのほかにも、新型コロナウイルス感染症が流行したころの臨時休校の対応として、学校給食で出せなくなったものを近隣の社会福祉施設に提供したという例もありました。
もちろん、そもそも食品ロスがないように、仕入れ時に鮮度をしっかり確認するということもされています。
こうした外部への引き渡しなどの活用ができるかどうかは、基本的に学校長の判断によります。学校自体が食品ロス問題に関心がある場合や、学校内に食品ロスへの意識が高い人が1人でもいるとその対応は変わってきます。
前述した活動は自治体や地域の方々との連携が必要なことですから、正直面倒な作業ではあります。それでも『なんとかロスしたものを活用しよう』という意識が高い学校で実施されているのだと思います。事実、こうした活動をしている学校はそれほど多いとは言えません」
——食用以外の用途としてロスしたものを使う場合は、どのような利用がされているのでしょうか。
「余った食材を堆肥にして校内菜園の肥料として使っている例はとても多いです。そのほか、学校で飼っているウサギなどのえさにしているという活用例もありますね。近隣にある動物園に寄付しているという例もあります。
それから、子どもたちが総合的な学習の時間の一環として、給食残さを花壇の肥料にするという活動を行っている事例もありました。職員が対応して終わらせるのではなく、子どもたちの学習の材料としても活用されているのは、子どもたち自身が普段食べているものに関心を寄せるいいきっかけですよね」
——食品ロス対策と食育やSDGsに関する教育が並行して行われる事例もあるのですね。
「そうですね。さらに、これは逆の発想ですが『ロスするはずだったもの』を給食に活用するという方法で食品ロスを減らしている事例もあります。
例えば、各学校では災害時に備えて用意している非常食のカンパンなどを定期的に入れ替えているのですが、入れ替えたものを給食の材料として活用している学校、ベジブロス(野菜の皮や切れ端)を使ってダシをとるという工夫をされたりしている学校などがあります。私も家でベジブロスを使ってスープをとることがあるのですが、とてもおいしいんですよ。カレーのスープに使ったり、リゾットに使ったりしています。
また、学校と地域の人が連携して互いに食品ロスを削減しようとする動きもあります。ある学校では、台風の影響で商品にできなくなったリンゴを農家さんから引き取って給食に活用したり、商品として規格外となってしまったゴボウの収穫体験を子どもたちがさせてもらい、給食に出したりするという事例もありました。
こうした活動は、学校と地域が相互に助け合うことで食品ロスを削減していく好例です。しかし、校内に調理室があり、柔軟に献立を工夫することができる学校でないとできないという側面もあります。どこの学校でもできることではありませんが、今後は地域と密接に連携した食品ロス対策にも注目、期待したいですね」