きょうだいがたくさんいても、勉強はできる
きょうだいがいるから家では勉強がはかどらない……中学受験をするきょうだいっ子からは、そんな声も聞こえてきます。しかし、8人きょうだいのオトクサさんの息子さんは、塾に通わずに中学受験の勉強をして、見事開成中学に合格! きょうだいがいることが、子どもの学習にプラスに働いたそう。
ここでは、『通塾なしで開成合格! 中学受験おうち勉強法』から「きょうだいのいる家庭ならではの勉強法」をご紹介。また、開成中のような難関校を目指すには、博物館や実験教室などの実体験をしたほうがいいのか? についてのオトクサさんの回答も取り上げます。
きょうだいのいる家庭ならではの勉強法
オトクサ家の場合、長男の受験直前期は「長男:6年生・次男:3年生・三男:2年生」、現在は「次男:5年生・三男:4年生・四男:2年生」という学年で中学受験に挑んでおり、3歳差・2歳差・1歳差の子どもの勉強を体験してきましたが、中学受験においては、一人っ子や年の離れたきょうだいがいる方が有利であり、親の負担も少ないのは間違いないと思います。しかし、その中でも見つけた、きょうだいならではのメリットについてお伝えします。
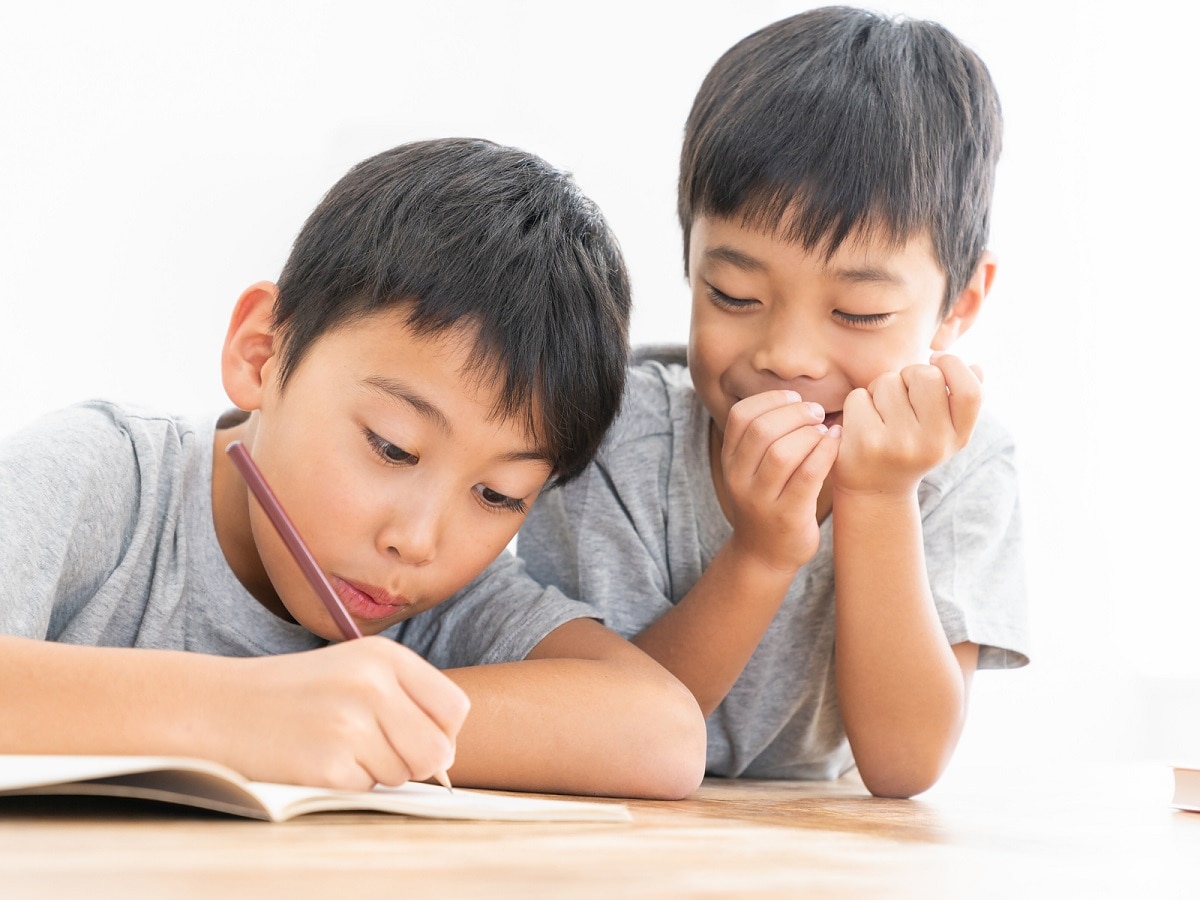
1.下の子に教えるのは一石三鳥
オトクサが外出中に算数でわからない問題があった場合、三男や四男は先送りにせず長男や次男に聞くことにしています。また、弟の勉強において、理科や社会の新単元のインプットを、あえて「兄が弟に教える」という学習法で実践したこともあります。これは、兄にとって決して時間の無駄ではなく、自分がすでに学習を終えている単元について、復習しながら曖昧な部分を見つけられるという効果もあります。弟も勉強になるし、オトクサが教える時間も省くことができる、まさに一石三鳥な勉強方法です。
2.学習習慣がつけやすい
きょうだいが同じ時間に勉強するので、自分だけ怠けるという意識は自然と少なくなるのかもしれません。朝起きなかったら他のきょうだいが起こすので、朝勉の支え合いにもなっていると思います。また、長男の勉強と遊び時間のバランスを見てきた弟達にとっては、それが当たり前です。次男や三男が、高学年になるにつれて1週間で友達と遊べる日数が減ることを受け入れていることはもちろん、いま1日中ゲームをしている五男も小学生になったら勉強しなくてはいけないことを理解しています。
兄が勉強で活用していたYouTubeや電子辞書を遊び道具として触っていたため、既に使い方を体得しているのも強みかもしれません。
3.きょうだいで楽しく競い合う
教育家の先生は、「きょうだいで比べてはいけません」と注意しますが、スポーツやゲームのように楽しく競い合うことで学習意欲が高まるメリットもあると思います。〈きょうだいで楽しく競うパターン〉
・同学年時の模試成績比較:テストの点数や順位について「お兄ちゃんに挑戦!」と目標にする
・学習時間の比較:勉強時間足りてないぞ~の声かけ
・計算や漢字勝負:アイツに負けるな! スピードや正確性の訓練
〈上の子の経験を活かすパターン〉
・4教科の勉強量のバランス:低学年時は理・社より算数の比重を圧倒的に高めよう
・教材や勉強法の見直し:上の子と同じことをすると苦手な分野がわかり内容を変えられる
・つまずきや重要ポイントの強化:兄の受験で学んだ重要ポイントを先取り学習できる
その他にも、書き込みをしていない問題集は、弟が活用できるという金銭的なメリットもあります。実際に次男の勉強では、『新演習問題集』以外はほぼ何も購入せずに、小学6年生を迎えようとしています。












