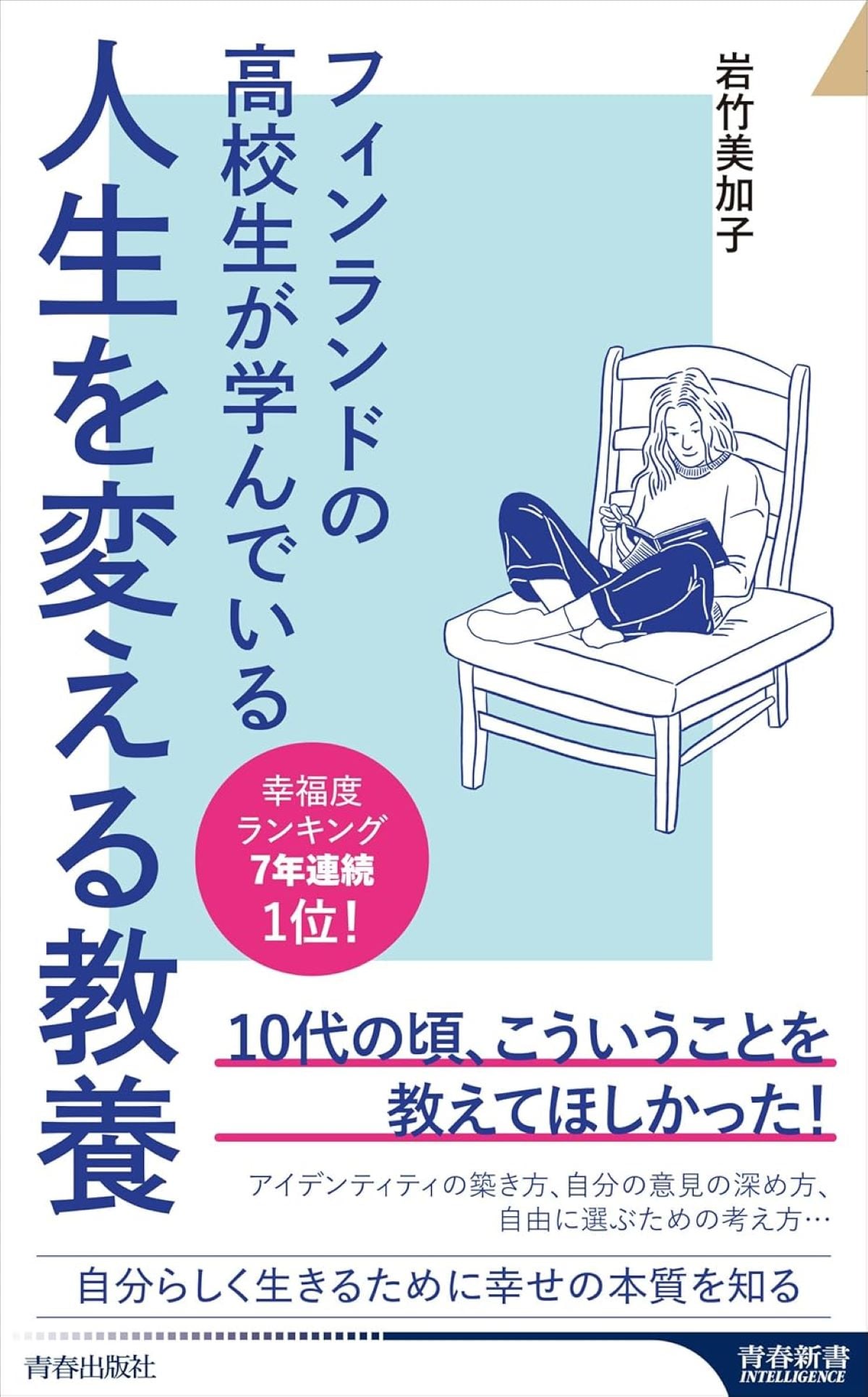学力テストや偏差値はない
フィンランドの学校には、学力テストや偏差値がないことも特長だ。そもそも、日本のような「学力」という概念がない。学力は、「学習を通じて獲得した知識」「学校の教科の授業を通じて獲得された能力」と説明される。しかし、フィンランドの教育が目指すのは「学習を通じて獲得した知識」というより、いかに学ぶかを学ぶことであり、その違いは大きい。学力テストなどでは測ることができないことが、重視されているのだ。学力テストや偏差値は、子どもに競争を課すものだが、競争と学ぶことに本質的な関係はない。もちろん子ども同士の遊びやスポーツで競争すること、楽しむことはあるだろうが、大人が介入して子どもを競争させるのは好ましくない、とするのがフィンランドの教育の考え方だ。
それは、子どものストレスや攻撃性を増したり、あるいは自分はダメだと感じさせたりするからである。競争や効率、経済性は新自由主義がもたらすものだ。新自由主義は世界的な潮流であり、フィンランドの教育にも影響を与えている一方、それを嫌う傾向が強い。
フィンランドでは、評価の方法として自分自身で評価するという方法が取られることが多い。ある課題について、自分の目的を設定し、終わった時にどれだけ達成したかを自分で評価する。また、グループである課題に取り組むときは、そこに参加した児童が評価するという方法だ。しかし、先生による評価も必要なので、学年の終わりには10段階の成績表が渡される。日本では5段階で評価され、それぞれのパーセントが前もって決められているが、フィンランドでは決められていない。
また、生徒個人について偏差値という考え方はない。偏差値は、テストを受けたグループの中での自分の位置を示す数字だ。例えば100点満点で90点を取って「良くできた」と思っても、同じ点数を取った子どもが多かった場合、偏差値は下がる。自己肯定感を挫くようなシステムでもある。しかし、子どもの能力は多様で、偏差値で測ることはできない。フィンランドの教育で、そうした数値化は意味あるものと考えられていない。
この記事の執筆者:岩竹 美加子
1955(昭和30)年、東京都生まれ。フィンランド在住。ペンシルベニア大学大学院民俗学部博士課程修了。早稲田大学客員准教授、ヘルシンキ大学教授等を経て、同大学非常勤教授 (Dosentti)。著書に『PTAという国家装置』(青弓社)、『フィンランドの教育はなぜ世界一なのか』(新潮新書)等がある。