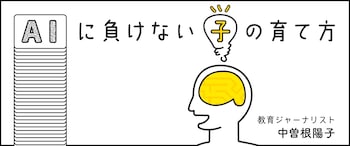噴火警戒レベルは「1」に
27日、長野・岐阜県境の御嶽山(おんたけさん)噴火から3年を迎えました。

御嶽山の噴火災害では、死者58人、行方不明者5人を出しました。気象庁は、8月21日に御嶽山の噴火警戒レベルを「2(火口周辺規制)」から、噴火発生時と同じ「1(活火山であることに留意)」に引き下げています。しかし、山頂付近の登山道などは荒廃したままであるといった理由から、王滝村など周辺地域は安全対策のため火口から約1キロ内の立ち入り規制を続けています。
御嶽山の噴火は、「戦後最悪の火山災害」とも言われています。この噴火があった9月27日に、改めて日本には多くの「活火山」があることについて理解を深め、噴火などに備える日にしてみてはいかがでしょうか。
活火山についてや、噴火が起きた時の対策などについては、アウトドアの専門家や災害危機管理アドバイザーがAll Aboutで解説しています。
**********
日本には活火山が多くある
アウトドアナビゲーターの渡部郁子さんによると、全国には110の活火山があり、そのうち「火山防災のために特に監視・観測体制の充実等が必要である」として火山噴火予知連絡会によって選定されている活火山を、気象庁が24時間体制で監視しているのだそうです。
気象庁が24時間体制で監視している活火山は50火山はあり、以下のとおりとなっています。
北海道地方
アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山
東北地方
岩木山、秋田焼山、岩手山、秋田駒ヶ岳、鳥海山、栗駒山、蔵王山、吾妻山、安達太良山、磐梯山、八甲田山、十和田
関東・中部地方
那須岳、日光白根山、草津白根山、浅間山、新潟焼山、焼岳、乗鞍岳、御嶽山、白山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、弥陀ヶ原
伊豆・小笠原諸島
伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島、硫黄島
九州地方
鶴見岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島
火山活動に関する警戒情報は気象庁が発表しており、全国110の活火山を対象に噴火警報・予報が発表されれば、気象庁サイト内の「防災情報」ページで確認できます。
登山するときの注意点・心構え
しかし、3年前に噴火のあった御嶽山は、気象庁で事前に火山性地震を計測していた活火山。渡部さんは「噴火の予兆とは判断されず、情報が公開されなかった“想定外”の噴火だった」と指摘しています。特に御嶽山は登山初心者も多く訪れる山で、噴火するまでは「警戒レベル1(平常)」だったことから、「御嶽山が活火山であることを知っていたとしても災害を予測し避けることは難しかったはず」と述べています。
渡部氏は社団法人日本山岳ガイド協会理事の竹内敬一氏の言葉を引用しながら、以下のような注意点を挙げている。
- 登山の際には危険をいち早く察知できるよう、周りの環境にアンテナを張り巡らせ、緊張感を持って臨むことが大切
- 活火山に登るときに登山者自身が気をつけることは、噴火警報の確認、ガスによる立ち入り規制などを忠実に守ること
- もし荷物に加えられるなら、携帯用の小ぶりの登山用酸素ボンベや花粉用のマスクを持ち歩くことで、ガスや火山灰から多少でも身を守ることができるかも
登山届を提出すること
災害危機管理アドバイザーの和田隆昌さんは、登山届の重要性について解説しています。
和田さんによると、御嶽山の噴火の際、提出されていた登山届が救助隊の安否確認や捜索救助活動に大きく役立ったことから、登山届の義務化が進んでいるとしています。登山届を出すためには、登山計画を立てることが必要となるので、メンバーの体力や装備、技術に合った登山を楽しむことにもつながるようです。
万が一噴火した時の対処法
和田氏は万が一、噴火した場合の対処法についても説明しています。
- 活火山周辺にいて噴火警報が発令された場合は、火口からの距離を置く退避方法が基本
- 逃げる間もなく噴石や火山れきが降ってくる場合はコンクリート製の屋内へとすぐに避難(活火山の火口周辺に火山弾を防ぐ避難シェルターなど避難場所があるか事前に確認しておく)
- なるべく稜線にあたる峰沿いに避難する方がリスクは低い
御嶽山の噴火発生時には有毒性のガスを含む高熱の「火砕サージ」による被害が発生した。噴煙は山麓の形状に沿いつつ、低地に向かって下降する傾向があるため、沢(谷状になっている底の部分)に降りずに、峰沿いがリスク回避になるという。 - 風向と共に噴煙の進行方向も目視しながら噴煙に巻かれないように避難方向を考える
活火山のリスクを考えながら観光すること
和田さんは、噴火予測は極めて困難だとしています。また、火口付近には火山性地震が頻繁に起きていない平常時においても、火山性の有毒ガスの発生など、一定のリスクは常に存在していることも忘れてはなりません。
一方で、日本国内には多くの活火山が存在しており、火山活動を起こしながらも周辺の住民はその恵みを享受して、一定の距離をおきつつ共に生活していることも事実です。
和田さんは、日本においては火山活動は避けられない自然現象とも言えるとし、「リスクを正しく認識した上で、発災時の対応をすれば被害に遭うことはありません。公開されている情報を入手して、安全と考えられる範囲で温泉や観光を存分に楽しみましょう」と述べています。
【関連リンク】